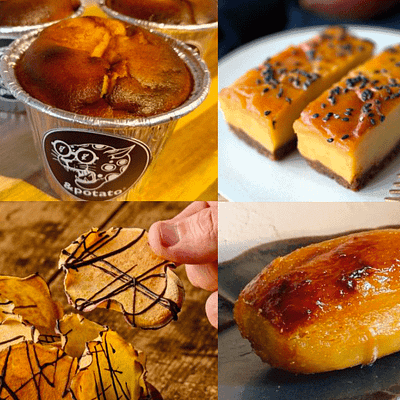家を出ると、外は相変わらずの激しい雨だった。暗い灰色の空を見上げ、傘を広げながら思う。「一体いつになったら晴れるのだろう」。連日の豪雨に、ふと先週のあの晴れた午後が恋しくなる。
記憶はあの日へと引き戻される。正午を過ぎても熱気が残る台北・西門町。コーヒーを片手に談笑する人々や、風景を写真に収める観光客で賑わう雑踏を抜け、私は目的地へと向かった。店に入ると、そこにはカメラマンの要求に応えてポーズをとる長身の影があった。彼こそが今日の主役、台湾野球界の伝説(レジェンド)――郭泓志(グォ・ホンジー)だ。
2025年7月に行われた台湾プロ野球(CPBL)のオールスターゲーム。私は外野席から、大型スクリーンに映し出される「夢の対決」を見つめていた。マウンドには王建民(ワン・ジエンミン)、打席には郭泓志。
郭が王の投球を捉え、ホームランを放った瞬間、球場は悲鳴にも似た歓声に包まれた。興奮した様子でダイヤモンドを一周する彼の姿は、私をあの台湾野球の黄金時代へと連れ戻してくれたようだった。
もしあなたが熱心な野球ファンでなくとも、彼の名は聞いたことがあるかもしれない。メジャーリーグで台湾人選手として初の本塁打を記録した男、「不死鳥」と呼ばれた左腕のことを。
台南から世界へ、「不死鳥」の飛翔
夢の芽は、台南野球場で育まれた。高校時代からその驚異的な剛速球で注目を集めた郭泓志の野球人生は、その球速と同じく規格外のものだった。
18歳で単身渡米し、メジャーリーグ(MLB)への挑戦を選択。それに伴う代表チームからの永久追放処分、度重なる肘の靱帯再建手術(トミー・ジョン手術)、長いマイナーリーグ生活……。
幾多の苦難を乗り越え、彼はメジャーのマウンドに立った。栄光の頂点も、怪我によるどん底も味わった。それでも彼は「努力し、決して諦めない」という精神を貫き、自らの居場所を勝ち取ってきた。その姿はまさに「不死鳥」。絶体絶命の淵から何度でも蘇る。
彼の物語は、私にこう問いかけてくる。「自分も夢のために、そこまでできるだろうか」。答えはまだ出ない。だが、彼の「夢を追う旅路」を知りたいという強い好奇心が、この野球人生を振り返り、人生哲学を探る対話の扉を開いた。
「もし戻れるなら、18歳のあのマウンドへ」
「もし人生のある一瞬に戻れるとしたら、いつを選びますか?」
人生は長い。私は内心、彼がメジャー初登板の瞬間や、あのホームランを打った時を選ぶのではないかと予想していた。しかし、彼は迷うことなく即答した。
「18歳。日本で松坂大輔と投げ合った、あの試合です」
彼にとってそれは、単に国の名誉を背負ったアジアAAA選手権(1998年)の決勝戦というだけではない。人生の大きな転換点だったのだ。
選手たちは幼い頃から過酷なトレーニングに耐える。野球人口は多いが、台湾のプロ野球に入れるのはほんの一握りだ。ましてや世界の舞台に立つチャンスなど、砂金を探すようなものだ。現在でも狭き門だが、20数年前はなおさらだった。
しかし、郭泓志は「貫き通すこと、後悔しないこと」という信念を胸に、ついに自分だけの輝ける瞬間を掴み取ったのである。
マウンドから山頂へ 「アウトドア愛好家」としての素顔
野球とは、勝者と敗者が残酷なまでに分かれる世界だ。マウンドに立つ投手であれ、バッターボックスに立つ打者であれ、選手は常に極限の心理的プレッシャーに晒されている。ふと疑問が浮かぶ。数々の修羅場をくぐり抜けてきた郭泓志は、その重圧とどう向き合い、解消してきたのだろうか?
「ストレス解消法は人それぞれです。ランニングでも音楽でも、自分に合った『出口』を見つけることが大事。私の場合は、それがアウトドアでした」
彼は少年のような笑顔で語り始めた。「キャンプ、登山、ウォータースポーツ……アウトドアと名の付くものは一通り挑戦しましたね」
彼にとっての「隠れ家」はどこなのか。「山ですね」と彼は即答する。「山にいると視界が開けて、心が解き放たれる感覚があるんです」
同じアウトドア愛好家として、私も深く共感した。都市の喧騒、交通渋滞、コンクリートのビル群から離れ、目の前に広がるのは連なる山々の稜線だけ。聞こえるのは自分の呼吸音と、虫や鳥のさえずりだけだ。自然と一体になり、内なる声に耳を傾けることができる。
郭氏の目には、野球とアウトドアは重なって映っているようだ。「どちらも『自分への挑戦』であり、『目標の達成』を目指すプロセスだからです」。
球場では自分自身に集中し、やるべきことを完遂する。アウトドアも同様に、登頂であれ波乗りであれ、自らが定めたゴールに向かって進む。その求道的な姿勢は、フィールドが変わっても変わらない。
「もし野球がなかったら?」 意外な答えと本音
人生の半分以上を野球という夢に捧げてきた彼に、あえてこう聞いてみた。「もし郭泓志の人生に野球がなかったら、何になっていましたか?」
彼は茶目っ気たっぷりに答えた。「応援団長になっていたかもね!」
思わず吹き出してしまった。彼がマイクを握り、スタンドを盛り上げている姿が目に浮かぶようだ。だが、この冗談めかした言葉には、彼の本質が隠されている。
「人々を楽しませたい」それが彼の根源的な欲求なのだ。選手を鼓舞し、ファンを熱狂させ、チアリーダーと共に踊り、「喜び(ハッピー)」を届けること。それができるなら、マウンドの上でなくても構わないのかもしれない。
自身の傷跡を「道標」に、子どもたちの夢を灯す
近年、台湾プロ野球(CPBL)は空前の盛り上がりを見せている。球場に足を運ぶファンが増え、野球への関心が高まっている現状に、郭氏も目を細める。
現役を退いた今も、彼の心はグラウンドにある。プロとして生きる過酷さを誰よりも知るからこそ、次世代を担う若者たちに「夢の種」を蒔きたいと願っているのだ。
今年、郭氏はアウトドアブランド「ティンバーランド(Timberland)」と協力し、地方の小学校を巡るプロジェクトを行った。子どもたちに自身の半生を語り、栄光と挫折、そして幾度もの手術を乗り越えた経験を伝えた。
「多くの困難があったけれど、信じ続けたのは『最後までやり抜くこと、全力を尽くすこと』だった」
彼は「これは仕事として『やらされている』のではなく、心から『やりたい』ことなんです」と真剣な眼差しで語った。
自身の傷だらけのキャリアを隠すことなく語り、地方の子どもたちに「君たちは一人じゃない。勇敢に夢を見れば、必ず晴れる日が来る」と伝える。そこには、台湾野球を愛する「偉大な先輩」の姿があった。
現役選手へ贈る、郭泓志流の「処方箋」
インタビューの終わりに、今まさに戦っている現役選手へのアドバイスを求めた。郭氏は真剣な表情に戻り、「夢を貫くこと。決して諦めないこと」と力強く語った。
さらに具体的な技術論が続くかと思いきや、彼はニヤリと笑ってこう付け加えた。
「もし疲れ果ててしまったら、顔を上げてチアガールを見てみるといい。きっとリラックスできるはずだよ」
またしても笑わされてしまった。台湾プロ野球といえば、華やかなチアリーダーによる応援が名物だ。冗談のように聞こえるが、これも極限の緊張感を知る彼ならではの、実用的なアドバイスなのだろう。「張り詰めるだけでは続かない、時には息を抜け」という、若者への優しさが滲んでいた。
「不死鳥」としての現役生活は幕を閉じた。しかし、郭泓志は今も「ネバー・ギブアップ」の精神を伝え続けている。かつて世界最高峰の舞台に立った男は、いま故郷・台湾の土の上で、自らの情熱を燃やし、後進の道を照らす「先駆者(パイオニア)」として新たな人生を歩んでいる。