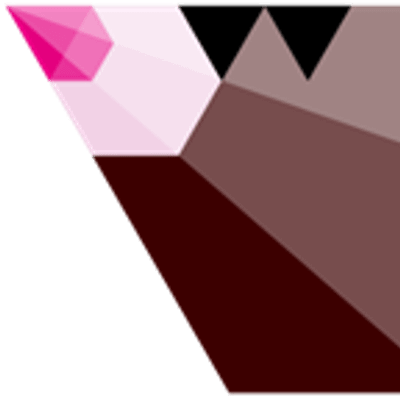トップ ニュース インタビュー》「平和教育」欠落する唯一の中国語圏 台湾元文化部長・龍應台氏「宝島のはずが、なぜ戦艦になったのか」
インタビュー》「平和教育」欠落する唯一の中国語圏 台湾元文化部長・龍應台氏「宝島のはずが、なぜ戦艦になったのか」 元文化部長の龍應台氏がインタビューに応じ、台湾は「平和ルート」を設計し、戦争への道を避けるために各方面が理性を発揮すべきだと呼びかけた。(写真/蔡親傑撮影)
台湾の元文化部長である龍應台氏は、『風傳媒』のインタビューで「欧米や日韓の子どもたちは幼い頃から“平和教育”を受け、対立をどう解決するかを学んでいる」と指摘した。一方で、中国語圏ではこの教育がほぼ欠落していると語る。特に台湾では「平和」という言葉が「降伏」と同義に扱われている現状に危機感を示し、「台湾は宝島であるべきなのに、なぜ戦艦になってしまったのか」と疑問を投げかけた。
龍氏は9月15日付『聯合報』に寄稿した「なぜ今、平和を語るのか」という特集記事の中で、平和は屈服ではなく「未来を自ら選ぶこと」であると強調。台湾は「第一列島線の最前線に立つハリネズミ」として犠牲になる必要はなく、平和を中国に委ねるべきでもないと主張した。台湾自身が主体的に「平和への道筋」を設計すべきだという立場を示している。
さらに、龍應台文化基金会は9月20日に台北で「2025台北国際平和持続フォーラム」を開催予定で、海外の活動家7人や台湾の学者、実務者を招き「なぜ平和のために努力するのか」を議論する場を設ける。
なぜ平和教育が欠かせないのか 龍氏は「脅威を感じない社会では、平和について考えることもない」と語る。基金会が初めて戦争をテーマに議論したのは2017年だったが、当時は社会の関心も薄く、「遠い問題」とみなされていた。だが数年後、戦争は身近で最も熱い議題となり、情勢は急速に緊迫している。
欧米では「平和学」が大学・専門家の研究分野として存在し、「平和教育」が一般市民、特に子どもたち向けに導入されている。幼稚園から始まる国もあり、日本や韓国でも重視されている。しかし、中国語圏の教育現場にはその要素がほとんど欠けていると龍氏は指摘する。
龍氏 によれば、平和教育は段階的に行われるべきものだ。例えば、子ども同士のいじめにどう向き合うか、教師の不公平な対応をどう受け止めるか、といった日常の中の対立から学ぶ。欧米の学校では立体地図を作り、子どもたちに「国」として役割を与え、対立を分析し、交渉や対話を体験させる教育も行われているという。
「なぜ台湾の教育にはこの重要な内容が欠けているのか」と龍氏は問いかける。職場の人間関係はもちろん、男女関係においてもそうだ。台湾社会では「恐怖の恋人」事件が繰り返されているが、その背景には対立をどう処理するかを学ぶ機会が極めて少ない教育環境があると警鐘を鳴らした。
龍應台氏は、西洋では平和教育が幼少期から始まっており、かつて侵略と被侵略の関係にあったドイツとポーランドでも青少年交流プログラムが始められたと語った。写真はポーランド・アウシュビッツ強制収容所。(写真/AP通信)
「平和」が「降伏」と同一視される現実 龍應台氏は、かつてドイツに滞在していた頃、小学校のクラスがポーランドに旅行し、現地の同世代の子どもたちと交流していたことを思い出す。第二次世界大戦後、ドイツとポーランド、あるいはフランスなど戦争当事国は大規模な青少年交流を開始し、次世代が幼い頃から「かつての敵国」の子どもと親しくなり、相互理解を深める機会を持つようにした。こうした取り組みは日本や韓国でも見られるが、「中国語圏だけが欠けている」と龍氏は強調する。
西洋の平和教育では、個人間の対立の解消方法、上下関係での不公平な扱いへの対応、自らの意見を主張しつつ他者を説得し、差異を尊重する技術が重視される。大学レベルになると、地域社会の衝突解決もテーマとなる。例えば湾岸に大型ホテルを建設する計画に環境団体が反対する場合、どのように交渉すべきかが議論される。また、就職を控える大学生には、職場でのいじめや上司との意見の衝突をどう処理するかといった教育も行われる。平和学は、子どもの人間関係から社会の職場、そして最終的には国家間の対立まで、あらゆるレベルで必要とされる学びなのだ。
龍氏は「台湾が『世界で最も危険な場所』と呼ばれながら、教育制度にも学術界にも平和教育が存在しないのは不可解だ」と語る。経済、文化、外交、社会、さらには軍事を含め、民主制度をいかに守るかを総合的に研究する発想が欠けていると指摘する。
また、自身が台南で8年間暮らした経験を振り返り、農民や漁民、先住民と交流する中で「善良な人々は誰も戦争を望んでいない」と確信したという。それでも台湾社会では「平和」という言葉が「政治的に正しくない」とみなされ、口にすることすらためらう風潮がある。その結果、今回の大規模なリコールの結果を見ても、社会の実態とネット上の世論には大きな隔たりがあると述べた。
龍應台氏は「平和」という言葉がすでに政治的に不正確とされ、大規模リコールの結果からも社会の実情とネット世論の大きな乖離が見て取れると指摘した。(写真/劉偉宏撮影)
軍備が目的化する危うさ 龍氏は「軍備は平和を実現するための手段にすぎない」と強調する。軍事力は確かに重要だが、それだけが解決策ではなく、経済面での戦略、教育による意識醸成、文化的な交流拡大、さらには政府間で対立しても市民同士の交流による道を模索することなど、多角的な努力が必要だという。ところが台湾では、軍事が唯一の語彙となり、広範でオープンな議論の場が欠けていることに危機感を示した。
さらに龍氏は、平和の反対は単なる戦争やイデオロギー対立ではないと指摘する。環境や生態のレベルでも平和は追求されるべきであり、両岸関係を政治的闘争だけに矮小化してはならないという。
例としてエチオピアとエジプトの関係を挙げる。ナイル川上流のエチオピアが大型ダム建設を宣言すると、下流のエジプトはただちに「武力行使も辞さない」と反発した。農業や工業、経済発展に直結するこの問題は国連が火薬庫として警戒する事態となった。同様に、メコン川では中国が上流で多数のダムを建設し、下流諸国の生存を脅かしている。最近では中国がヤルツァンポ川で水利施設を建設すると発表し、下流のインドが強い警戒感を示している。水資源の配分という一見技術的な課題でさえ、重大な戦争の火種となり得るのだ。
エチオピアで建設された巨大ダムは、下流国エジプトの強い反発を招いている。(写真/AP通信)
平和の定義を広げるべきだ 龍應台氏は、歴史研究の知見として、古代ローマ帝国から中国の秦・漢以降の二千年にわたる王朝の交代を比較した学者の分析を紹介する。その結論は一貫しており、大規模な災害の発生はしばしば革命や政権崩壊を引き起こす要因となるという。特に干ばつは洪水と比べ、暴力的な革命や王朝転覆につながる可能性がほぼ倍に達するとの結果が出ている。最近出版された研究書でも、明朝の崩壊は当時の気候変動による資源不足や土地荒廃に起因していたと指摘されている。龍氏は、平和の議論において政治やイデオロギーだけでなく、環境への姿勢や資源管理のあり方を含めて考えるべきだと強調する。
台湾が直面している課題として、龍氏は2021年に起きた深刻な干ばつを例に挙げ、もし同様の事態が繰り返されれば社会の脆弱性が浮き彫りになると警鐘を鳴らす。また、食料問題も深刻で、台湾の食料自給率は2023年時点でカロリー換算30.3%と過去18年で最低水準に落ち込んでいる。特に大豆やトウモロコシは9割以上を輸入に依存しており、もし封鎖が起これば食料不足が深刻化するのは避けられない。龍氏は「平和を守るために武器だけを論じるべきではない」と語る。
龍氏 はまた、龍應台文化基金会が近年「平和」という観念を推進してきた背景に触れ、多くの台湾人が「共産主義下では生きたくない」という願いを抱いていることを指摘する。台湾社会は世界の中でも特異で貴重な存在であるにもかかわらず、平和や安全の定義が極端に狭いことに疑問を呈し、軍備のみを問題の核心とするのは誤りだと警告した。
龍應台氏は、台湾にはより深い研究と賢明な判断によって「平和の道筋」を設計する必要があると強調した。(写真/蔡親傑撮影)
台湾は「平和の道筋」を設計すべきだ 龍氏は、平和の道筋は深い研究と冷静な判断の上に設計されるべきだと語る。相手が極めて非合理的な場合、合理的な場合、それぞれに応じた戦略が必要であり、社会全体で幅広い議論を展開し、政府が情報を独占するのではなく国民と共有する必要があると訴える。国民は恐れて議論を避けてはならず、政府は準備を怠ってはならないという。
軍備のあり方、エネルギーや水資源、産業発展、文化交流や民間の善意など、多方面にわたる要素を総合的に検討し、「平和の道筋」として設計すべきだと主張する。しかし現実には、こうした議論を口にするだけで「中国寄り」とレッテルを貼られ、社会に恐怖が広がる。結果として、国民は無自覚のまま「戦艦」に乗せられてしまう。「台湾は宝島であるべきなのに、なぜ戦艦になってしまったのか」と龍氏は問いかける。
龍氏 はまた、協力の可能性に言及する。中研院が2022年に人類史上初のM87ブラックホールの画像を撮影できたのも、5つの国際チームの協力があったからこそだと例を挙げる。司法や犯罪対策、気候変動による温暖化、海面上昇、森林火災や河川汚染といった問題も、二国間や国際的な協力なしには解決できない。「武器に頼るだけでは意味がない」と断じた。
さらに龍氏は、平和を担う最大の責任は強者にあるが、弱者も黙っていてはいけないと述べる。たとえ相手が圧倒的で不条理であっても、暴力で対抗する道だけでなく、知恵で立ち向かう方法もあると強調した。
龍應台文化基金会は9月20日に「2025台北国際平和フォーラム」を開催し、龍氏は「なぜ今、平和を語らなければならないのか」というテーマで基調講演を行う予定である。
更多新聞請搜尋🔍風傳媒日文版
最新ニュース
池袋「GiGO総本店」が開業2周年 9月20日から記念キャンペーン開催 株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区)は、東京・池袋にある旗艦店「GiGO総本店」が9月20日に開業2周年を迎えるにあたり、同日から記念キャンペーンを実施すると発表した。池袋の旗艦店「GiGO総本店」が9月20日に開業2周年を迎え、限定グッズの販売や特別イベントなど記念キャンペーンを実施する。(写真/GiGO提供)947......
クナイプ、新製品発売記念イベント「ドイツのくすり湯」 9月18日から大崎・金春湯で開催 ハーバルブランドのクナイプ(株式会社クナイプジャパン、本社:神奈川県横浜市)は、肩や腰のケアに用いられる天然ハーブ・アルニカエキスを配合し、パワーアップリニューアルした『グーテエアホールング バスソルト ジュニパー&アルニカの香り【医薬部外品】』の全国発売(9月16日)を記念して、9月18日(木)から23日(火・祝)までの6日間、東京・大崎の老舗銭湯「金春湯......
トランプ氏と習近平氏が6月以来の直接対話へ 台湾問題とTikTok規制が焦点に トランプ氏と習近平国家主席が近く電話会談を行う予定であり、その内容に大きな関心が寄せられている。共和党の下院議員モーレナール氏は、この会談にはあまり期待していないと述べ、象徴的な意味合いにとどまる可能性があるとの見方を示した。会談で台湾問題が取り上げられるかどうかは不明としつつも、台湾は米国民にとって重要な関心事であり、トランプ氏にとっても同様であると強調し......
台湾立法院で民進党新体制発表 柯建銘氏が総召を続投、幹事長・書記長も決定 台湾民進党の立法院党団幹部改選が本日(19日)に行われ、総召(党団代表)の柯建銘氏が引き続きその地位を守ることに成功した。幹部チームの顔ぶれも正式に決まり、新会期では鍾佳濱氏が幹事長に就任し、陳培瑜氏が書記長を続投する。今回の布陣は、派閥間の力学の均衡を映すとともに、頼清徳総統が党団運営に強い関心を示していることを示唆している。柯建銘氏が総召を続投できた背景......
トランプ政権が台湾向け4億ドル軍事援助を一時停止 米中首脳会談への譲歩の恐れ 米紙ワシントン・ポストは関係者5人の証言として、米国のトランプ大統領が中国の習近平国家主席との貿易協議や首脳会談の可能性をにらみ、今夏、対台湾向けの軍事援助4億ドル(約592億円)超の承認を拒否したと報じた。ホワイトハウス当局者は「この援助計画の決定は最終的に固まっていない」と強調し、台湾の駐美代表処はコメントを控えた。今回の判断は、ワシントンの対台湾軍事支......
速報》台風18号(ラガサ)最新進路予測 北部も強風・豪雨に注意、沿岸部では10級超の突風か 勢力の強い台風が台湾に接近している。最新の気象情報によれば、台風18号(ラガサ)は現在、台東県の南東約1,400キロの海上に位置し、徐々に発達している。予測では、来週23日(火)にバシー海峡を通過する際に強さのピークを迎え、中度台風、さらには強い台風へと発達する可能性がある。台湾への影響と風雨の時系列台風18号が台湾本島を直撃する可能性は比較的低いとされるも......
OpenAI、未成年専用「ChatGPT」導入へ 米訴訟受け安全対策を強化、保護機能も拡充 生成AIの普及が急速に進む一方で、倫理や法律をめぐる議論が相次いでいる。特に今年4月、米国で「AIが少年を死へと誘導した」とされる訴訟が明らかになり、社会に衝撃を与えた。この事件を受け、ChatGPTを運営するOpenAIは、成人と未成年の利用を区分する新方針を打ち出し、再発防止に向けた安全対策を強化することを決定した。未成年専用「適齢版ChatGPT」の提......
《ワシントン・ポスト》独占報道:トランプ氏、習近平氏との取引で台湾軍事援助4億ドル停止か 《ワシントン・ポスト》は18日、トランプ政権が対中貿易協定を得るため、台湾への軍事援助を棚上げする方針を独占的に報じた。これは米国の対台湾政策における重大な転換とみなされ、安全保障の専門家の懸念を呼んでいる。《ワシントン・ポスト》の報道によれば、事情に詳しい少なくとも5人の関係者が明らかにしたところでは、米国のトランプ氏は今夏、台湾への総額4億ドルを超える......
クナイプ「グーテエアホールング バスソルト」リニューアル アルニカ新配合で一部店舗先行発売 ハーバルブランド「クナイプ」を展開する株式会社クナイプジャパン(本社:横浜市、代表取締役社長:大脇明憲)は、ロングセラー商品「グーテエアホールング バスソルト」をパワーアップリニューアルし、「グーテエアホールング バスソルト ジュニパー&アルニカの香り【医薬部外品】」を一部小売店(スギ薬局)にて先行発売すると発表した。今年、日本上陸40周年を迎える同ブランド......
山手線環状運転100周年記念フェス開催 復刻ラッピング列車や特別観光列車が登場 東日本旅客鉄道(JR東日本)は、山手線が環状運転を開始してから100周年を迎えるのを記念し、「つながる山手線フェス ~環状運転100周年~」を10月4日から11月3日まで開催すると発表した。期間中、山手線各駅や沿線施設で鉄道イベントや地域とのコラボ企画、音楽・アート関連の多彩な催しが行われる。JR東日本は、山手線環状運転100周年を記念し、復刻ラッピング列車......
「日本の祭りはどう守る?」石垣悟准教授が語る持続可能な継承の形と課題 公益財団法人フォーリン・プレスセンターは9月12日、「日本の祭りを守る」をテーマにオンラインブリーフィングを開催し、國學院大學観光まちづくり学部の石垣悟准教授が登壇した。石垣氏は長年にわたり日本各地の祭りを研究・記録してきた経験をもとに、現代における課題と継承の可能性を語った。「守る」とは形を固定することではなく「続ける」こと石垣氏はまず、伝統的な祭りは地域......
小和田恆氏、戦後80年の日本外交と課題を語る「被害だけでなく加害の視点も必要」 日本記者クラブで9月12日、「戦後80年を問う」シリーズ第18回が開催され、元国際司法裁判所(ICJ)所長であり元外務事務次官の小和田恆氏が登壇した。93歳を迎えた小和田氏は、自らの外交経験を交えながら戦後日本外交の軌跡を振り返り、歴史認識や安全保障、さらには地球規模課題に至るまで幅広く論じた。受難と加害の視点小和田氏は、戦後80年の節目に各地で報じられる記......
大谷翔平、164キロ剛速球&50号本塁打 史上初「50本塁打・50奪三振」の偉業達成 ロサンゼルス・ドジャースの二刀流スター、大谷翔平が再びMLBの歴史に名を刻んだ。17日(現地時間)の本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦で先発登板し、5回を無安打無失点、5奪三振の圧巻の投球を披露。さらにシーズン50号本塁打を放ち、史上6人目となる「2年連続50本塁打」に到達した。同時に、自身初の「シーズン50本塁打・50奪三振」という前人未到の記録を樹立し......
「トリプル台風」接近の恐れ 台風17号・18号・19号が相次ぎ発生か 台湾中央気象署は18日、第20号熱帯低気圧や台風外側の環流の影響で、台東や恒春半島で雨や雷雨の頻度が増し、局地的に大雨や豪雨となる可能性があると発表した。南部や東部も短時間の雷雨が見込まれ、特に台風18号(ラガサ)が中規模以上の台風に発達し、強風と豪雨を伴う見通しだという。さらに熱帯低気圧TD22も台風19号(ノグリー)に発達する恐れがあり、台湾周辺で複数の......
「ポケモン東京ばな奈」5周年記念 ピカチュウが巨大クッションに!抽選で25名限定プレゼント 「ポケモン東京ばな奈」5周年記念キャンペーン株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開する人気土産ブランド「東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の誕生5周年を記念して、『ピカチュウ東京ばな奈クッションセット』が当たる特別キャンペーンを実施する。応募は2025年9月10日(水)10:00から23日(火・祝)23:59まで、公式X(旧Tw......
「二重速度経済」が鮮明に 米国で高所得層だけ賃金上昇、若者はAIで雇用喪失の危機 パンデミック期に一時縮小した米国の貧富の格差は、2025年に入り再び急速に拡大している。高所得層や資産を持つ高齢世代は、株式市場や不動産市場の高騰による恩恵を受け、旺盛な消費力を誇示している。一方で、低賃金労働者や若い世代は、賃金の停滞や失業率の上昇という厳しい現実に直面している。《ウォール・ストリート・ジャーナル》は16日、このような「二重速度経済」の現象......
環境危機時計が8年ぶりに大幅進行 地球環境アンケートで「9時33分」に悪化 公益財団法人旭硝子財団は9月10日、世界の環境有識者を対象に実施した「第34回 地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の結果を発表した。1992年から毎年続けられている調査で、今年は202カ国に調査票を送付し、121カ国から1,751件の回答を得た。公益財団法人旭硝子財団は9月10日、世界の環境有識者を対象に実施した「第34回 地球環境問題と人類の存続......
船場×Autodeskが戦略的提携 内装業界のDX加速とBIM普及を推進 空間創造企業の株式会社船場(東京都港区、小田切潤社長)は8月27日、米国Autodesk社と「戦略的提携に関する覚書(MOU)」を締結した。共通データ環境(CDE)の構築と業務プロセス改革を通じ、内装業界におけるDX推進とBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の普及を目指す。本提携により、船場はAutodesk Construction Cl......
大谷翔平「OHTANI DAY」第5弾 直筆漢字サイン入り公式球を限定1点で抽選販売 世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを展開する Fanatics Inc. の日本法人・ファナティクス・ジャパン合同会社は、毎月17日に実施する特別企画「OHTANI DAY」の第5弾として、「大谷翔平シグネチャー・コレクション」を抽選販売すると発表した。今回の目玉商品は、大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャース移籍後に初本塁打を記録した 2024年4......
MLBポストシーズン2025記念グッズ発売開始 ブルワーズ進出・フィリーズ優勝Tシャツ登場 世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを展開する Fanatics Inc. の日本法人・ファナティクス・ジャパン合同会社は、2025年10月1日(日本時間)に開幕する 「MLBポストシーズン2025」オフィシャルグッズ を、9月16日よりMLB公式オンラインショップにて販売開始した。ナショナル・リーグでは、9月13日に ミルウォーキー・ブルワーズ の......
じゃがボルダが“二刀流”に進化!東京駅限定チップスに新作「さつまいも」登場 株式会社グレープストーン(東京都中央区)とカルビー株式会社(東京都千代田区)は、両社が共同開発した進化系ポテトチップスブランド「JAGA BOULDE(じゃがボルダ)」の東京駅限定店舗を2025年にリニューアルオープンすると発表した。「じゃがボルダ」は、カルビーのアンテナショップ「Calbee+」と東京土産ブランド「東京ばな奈」がコラボレーションして誕生した......
コロナ セロに缶タイプ新登場 9月24日から全国販売、先行販売も開始 世界的ビールブランド「コロナ エキストラ」を展開する AB InBev Japan 合同会社は、アルコール0.0%のノンアルコール飲料「Corona Cero(コロナ セロ)」に新たに缶タイプを追加し、2025年9月24日(水)から全国で販売を開始する。これに先立ち、9月8日(月)から一部のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにて先行販売が始まっている。......