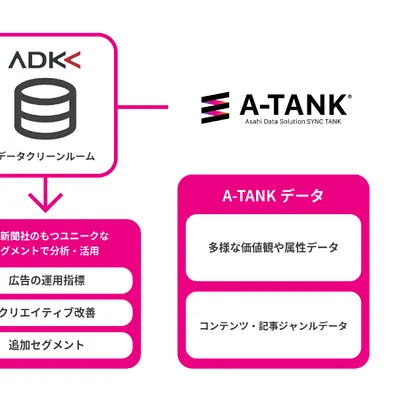日本政府は12月23日、メガソーラーを中心とする太陽光発電の拡大路線を見直す方針を示した。早ければ2027年度以降、大規模太陽光への支援策を廃止し、再生可能エネルギー賦課金による補助も打ち切る方向だ。あわせて環境影響評価(環境アセスメント)を厳格化し、各地で土地を囲い込んできた開発業者にとっては、事実上の「退出を促す強いメッセージ」となる。
3.11東日本大震災後に加速した太陽光導入とその歪み 2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に、日本は再生可能エネルギーへの転換を急速に進めた。中でも太陽光発電は「安全でクリーンな電源」として期待を集め、2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)が投資を一気に呼び込んだ。
その結果、山林を切り開き、湿地を埋め立ててまで太陽光パネルを設置する大規模開発が各地で相次いだ。制度を支える財源として、電気料金とともに徴収される「再生可能エネルギー賦課金」が用いられ、国民全体がそのコストを負担する構図が定着した。
しかし、導入から10年以上が経過する中で、この仕組みは次第にひずみを露呈するようになった。
2024年2月11日、損傷した福島第一原子力発電所。(AP通信)
2024年8月21日、韓国の環境団体メンバーが、福島第一原発の処理水放出をめぐり在韓日本大使館前で抗議した。(AP通信)
12月23日の関係閣僚会議で、内閣官房長官の木原誠二氏は、太陽光発電が国内総発電量のおよそ1割を占めるまでに拡大したと説明した。その一方で、「一部地域における大規模発電計画が、自然環境や安全、景観の面でさまざまな懸念を招いている」と指摘した。 木原氏は、再生可能エネルギーの導入は地域との共生と環境への配慮を大前提とすべきだと強調した。地域と調和する事業は促進する一方で、無秩序な開発や不適切な事業については、厳格に対応する必要があるとの認識を示した。
高市早苗政権は、メガソーラーに対する支援策の廃止に加え、環境アセスメントの対象拡大も検討している。現在は出力4万キロワット以上の発電施設が対象となっているが、これを3万キロワット以上に引き下げる案が浮上している。 さらに、日本政府は『種の保存法』で定める保護区域の拡大や、国立公園の管轄範囲を広げることも視野に入れている。これにより、大規模太陽光発電の開発予定地に含まれる希少生物の生息環境を、より広く保全する狙いがある。
NHKは、今回の一連の方針について、政府がこれまで強力に後押ししてきた太陽光中心の再生可能エネルギー政策が、明確な転換点を迎えたことを示していると伝えている。
こうした規制強化と並行して、日本政府は次世代技術の導入にも活路を見いだそうとしている。その一つが「ペロブスカイト太陽電池」だ。ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を持つ材料を溶液化し、薄膜やガラス基板に塗布して製造するこの電池は、軽量で柔軟性が高いのが特徴とされる。
現時点では量産コストや耐久性といった課題が残るものの、建物の外壁や耐荷重の低い屋根にも設置できる可能性があり、従来型の大規模用地開発に依存しない太陽光発電の選択肢として期待が集まっている。
「グリーン破壊」と批判 釧路湿原と鴨川が示した現実 では、なぜ日本政府はここまで踏み込んだ対応に動いたのか。 NHK は、その背景として、太陽光発電所の開発が地域住民の十分な理解を得ないまま進められ、各地で不安や反発が広がった点を挙げている。報道では、北海道と千葉県で起きた事例を「警鐘」として詳しく紹介した。
北海道の釧路湿原国立公園周辺は、タンチョウなど希少な野生生物が生息する地域だが、近年は太陽光パネルが集中的に設置される事態となった。開発事業者が知事の許可を得ずに工事を進めたり、虚偽の申請を行ったりするケースも相次いだ。本来は環境負荷を減らすはずの再生可能エネルギーが、逆に生態系を脅かす存在になったとの指摘が強まっている。
釧路湿原国立公園周辺に設置された大規模太陽光発電施設(メガソーラー)。(日本環境省公式サイトより)
一方、千葉県鴨川市の山間部では、東京ドーム約31個分にあたる146ヘクタールの超大型太陽光発電計画が進行し、住民の不安を招いた。事業を手がける「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」は、今年5月から伐採を進めたが、県は未許可区域で工事が行われていたことを確認した。
「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」の関連資料。(同社公式サイトより)
千葉県は10月、事業者に対して行政指導を行い、無許可区域での伐採を指摘。現在、工事は一時停止している。自然資源エネルギー庁も、日本国内で大規模太陽光発電に適した平坦地は限られ、多くがすでに開発済みだと説明する。NHKは、こうした状況を受け、自治体が相次いで条例を制定し、地域との調和を前提とした再生可能エネルギー導入を求めていると伝えた。
拡大一辺倒だった再エネ政策への反発 2011年の東日本大震災と福島第一原発事故後、日本政府は太陽光発電を中心とする再生可能エネルギー拡大政策を進めてきた。大手電力会社には、発電コストを上回る価格で再生可能エネルギー電力を買い取ることが義務づけられ、導入は急速に進んだ。
自然資源エネルギー庁によると、再生可能エネルギーの発電比率は2011年度の10.4%から、直近では23%に上昇。このうち太陽光発電が最大で、総発電量の9.9%を占めている。出力1000キロワット以上のメガソーラーも増え、今年3月末時点で、8,995施設が国の認定を受けている。
今回の政策見直しについて、長年、法整備と自然保護の強化を訴えてきた釧路市の鶴間秀典市長は、釧路湿原国立公園の区域拡大が法案に盛り込まれた点を「地域の声に応える動きだ」と評価する。地域と共生できない事業者に対しては、実効性のある歯止めになるとの見方を示した。
釧路自然保護協会の神田房行会長も、「再生可能エネルギーそのものに反対ではない」としたうえで、「釧路湿原のような環境が損なわれないことが前提だ」と強調。太陽光発電を進める区域と、守るべき区域を明確に分ける必要性を訴えた。
鴨川市の80代の男性はNHKに対し、「鴨川で最も大切なのは自然だ。メガソーラーのために自然を壊すことには反対だ」と語った。70代の別の男性も、「原発への不安はあるが、環境保護と太陽光発電の両立は簡単ではない。慎重な判断が必要だ」と話している。
エネルギー経済社会研究所の松尾豪氏は、「政府の支援制度は再生可能エネルギー普及に大きく寄与した」とした上で、「適地が減る中、条件の悪い場所への建設が増えている。事業モデルも成熟しており、補助終了は合理的だ」と指摘する。
また、環境大臣の石原宏高氏は23日の閣議後、「再生可能エネルギーの導入は、環境への配慮と地域共生が大前提だ」と述べ、「2050年のカーボンニュートラル実現に向け、関係省庁と連携して対策を進める」と強調した。