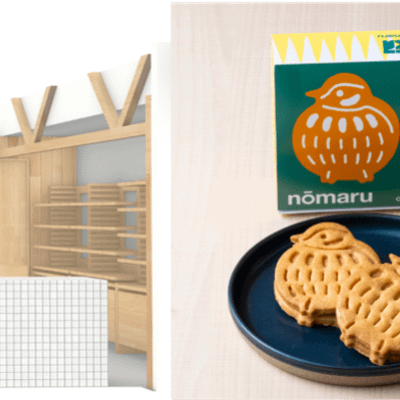司法が一度でも独立と公正から逸脱すれば、それは最も冷酷な国家暴力となる。台湾は民主社会を標榜しているが、柯文哲氏の事件で論争を呼んだ度重なる勾留延長や取り調べ手法から、リコール署名をめぐり全国で二十人以上が拘束された事例に至るまで、繰り返し「濫権」が正義の衣をまといながら、手続きと人権を踏みにじる場面が見られてきた。政治的な勾留が懲罰と化し、取り調べが辱めとなり、司法制度が抑制と均衡を失うとき、民主主義の最後の防波堤はすでに空洞化している。これは個別の悲劇ではなく、制度全体への警鐘である。事実、台湾社会はすでに司法への最も基本的な信頼を失っている。
台北地方裁判所は柯氏の勾留延長審理を六度にわたり開くこととなった。柯氏の妻、陳佩琪氏は連日フェイスブックに投稿し、「司法は社会の公平と正義を守るためのものであり、政敵を抹消する道具ではない」と訴えた。公人の妻として、陳氏はかつて十二万件を超えるシェアを集め、選挙応援の拍手を浴びる日々を経験した。しかし彼女は、柯氏が土城の拘置所で苦しむ一方、自らも家庭で苦悩する日が訪れるとは想像もしなかっただろう。司法が正義の旗を掲げるとき、どれほどの人が人権を顧みるのか、あるいは被疑者の家族が背負う重圧を考慮するのか。前台北市副市長の彭振聲氏の妻は、断固とした態度で司法に背を向けた。それは彼女の無言の告発であった。しかし、その声は司法に一切の反響を呼ばず、ましてや反省を促すこともなかった。
人民の陳情が利益になるとは─誰がそんな法解釈を?
陳佩琪氏のいわゆる「庶民の問い」は、まさに「司法の根本的な問い」として位置づけられる。たとえば「捜索の理由は何か、それは被捜索者に明示されるべきではないか」という点である。陳氏は検察官に感謝すべきなのかもしれない。少なくとも捜索令状には「貪汚治罪条例」と記されていたからだ。一般の検察・警察が発する召喚状は、年度や番号、部門名があるだけで、召喚を受けた側はほとんど理解できない。出廷して「証言」をしても、何を証言させられるのか分からないままなのである。陳氏自身、二度目の訊問の際に「賄賂の録音を傍受したのか、それとも現金入りのバッグを持った人物が官邸に入るところを撮影したのか」と尋ねたことがある。これは、かつて桃園市長だった鄭文燦氏の事案を引き合いに出したもので、現金の入ったバッグを官邸に持ち込む様子が撮影されながら、証拠として提出されなかった事例を踏まえた問いかけであった。だが、検察官の答えは「事証はあるが、あなたには教えない」というものだった。
検察官に誤りはあるのか。実際にはない。これこそが検察官の日常的な捜査手法である。司法改革を経て裁判所における検察と弁護側の地位は形式上は対等とされたものの、検察官は決して当事者と自分を同列と見なさない。むしろ、検察官は「司法権力」を高く掲げ、国家を代表して個人を訴追する存在である。裁判官が独自の心証を持つ場合や、検察官自身が権力あるいは権力者に特別な欲望や幻想を抱かない限り、検察官の行為を抑制できる者はほとんどいない。そしてもし検察官の行為が権力や権力者の影響を受ければ、その結果は今日目の当たりにしている姿である。すなわち、司法が政治に奉仕し、国家機構が人権を圧迫する凶器と化す。検察官を抑制すべき裁判官すら、検察官や政治的配慮に従属する「付随物」となり、「司法の公平」は絶望の淵に追いやられる。
検察官は「証人」である陳氏に対し、いかなる「事証」も伝えないことができる一方、「被告」には違法行為を繰り返し指摘することができる。例えば、被告とされた四人のうち彭振聲氏は、京華城の容積率は合法だと今も主張しているにもかかわらず、四か月にわたり勾留され、三十回以上も取り調べを受けた。その過程で検察官は繰り返し「市民の陳情を検討に回すこと」自体が「利益供与」にあたると指摘し続け、ついには彼は「罪」を認めるに至った。誰が検察官に、このような「法律専門性」を与えたのか。
暗号通貨、ATM預金、自宅に三億の現金─誰が陳佩琪氏に謝罪する?
《行政手続法》および各機関の「陳情案件処理要綱」に照らせば、行政は単に検討するだけでなく、面談や現地調査を行い、さらに陳情者へ文書で回答することも認められている。常識的に言えば、官員が市民からの陳情を無視すれば、監察院による調査や弾劾の対象となる。実際、監察院は京華城案件について、容積率の基準が過度に厳しいとして最初の糾正を行っている。邵琇珮氏もまた、手続きはすべて合法であると主張していたが、検察官から「公務員としての地位が危うくなる」と示唆されると、最終的に認罪に応じざるを得なかった。
京華城に関わる朱亞虎氏や陳俊源氏の場合も、いわば「認罪」と引き換えに勾留停止や起訴猶予を得る形となった。要するに、検察官は伝統的に威嚇や利益誘導を捜査手段として用い、「勾留」は供述や自白を引き出すための最も手軽な武器となっているのである。しかし、その濫用がもたらす結果は証拠不十分であり、罪状も断片的なものにとどまる。起訴は粗雑で、人を押さえ込むことは恣意的である。このような司法に、国民がどうして信頼を寄せられるというのか。
最も深刻なのは、「党・検・メディア」が粗雑な起訴に呼応し、「捜査の非公開」を茶番にしている点である。1年前に大々的に報じられた内容が、1年後に台北地裁で六度目の勾留延長審理を前に、再び繰り返し報道された。「党・検・メディア」は、実態として「捜査全面公開」という悪弊に加担している事実を省みようとせず、当事者にとっては消し去ることのできない烙印となっている。
陳佩琪氏が自ら言及しなければ、多くの人々は忘れていただろう。昨年、「党・検・メディア」がいかに彼女のATMでの「入金行為」を揶揄し、不自然な動きと決めつけたかを。問題はこうである――誰が知っていただろうか。ATMへの入金について、一週間以内に他口座からの出金記録を提示できなければ、「財産の出所不明罪」とされ得ることを。さらに、彼女が市庁舎での議員弁当会の八日後に、子どもの投資口座に資金を入金しただけで「賄賂」と断じられた。
陳氏は大量の通帳を抱えて国税局に赴き、息子との間に長年にわたる贈与や投資行為があったことを立証した。息子がかつて八百十万元で彼女名義の旧マンションを購入しており、直系親族間の不動産取引として免税証明も取得していたことも示した。彼女は全力で「無実の証明」に努めざるを得なかった。それもすべて、「党・検・メディア」の陰湿な示唆や憶測のためである。果たして、誰が彼女に謝罪を返すのか。
陳佩琪氏は吳淑珍氏ではない─検察官は自分の欲しい図しか描けない
事実として、これらの入出金や「投資」にはすべて具体的な経路と口座があり、検察当局の徹底的な調査から逃れられるものは存在しない。検察官が資金の流れを突き止められず、「党・検・メディア」も金流の経路を押さえられない中で、ついには「仮想通貨」にまつわる荒唐無稽な話まで仕立て上げられた。仮想通貨では不十分と見たのか、柯文哲氏の秘書「橘子」の交際相手による証言として、「柯家には常時六千万元から三億元の現金がある」との話まで飛び出した。
しかし、陳佩琪氏は取調べの場でこれを「全くの捏造」と断言し、まずは自宅周辺の百本以上の監視カメラを調べ、現金があるはずならいつ搬出されたのかを確認すべきだと求めた。さらに彼女は、自らの供述調書を起訴状と併せて裁判所に提出するよう要求した。「今のままでは弁護人ですら私の調書を見つけられない」と訴えたのである。にもかかわらず、検察官は一人の偏った証言を物的証拠なしで起訴状に盛り込み、逆に柯文哲氏に有利な陳氏の調書は記録すらしなかった。なぜか。検察官は陳氏を「呉淑珍2.0」と想像したのかもしれないが、彼女はそうではない。
検察官は自分が望む「犯罪像」だけを描いてよいのか。刑事訴訟法には、検察官は被告に有利な証言を無視してはならないと明記されている。そうであれば、すでに検察官は「違法」に足を踏み入れているのではないか。陳氏の証言に限らず、すでに「認罪」した被告を含め、柯氏に有利な証言が他にも存在する。それを検察官はなぜ一切採用しないのか。
柯文哲氏は新興政党の代表であり、大統領候補者でもある。法律上、政治献金を受け取ることは認められており、仮に申告に不備があったとしても行政罰にとどまる。検察官は明確な証拠がない限り、政治献金を「賄賂」と短絡的に結びつけることはできない。ましてや、選挙と京華城の容積率緩和案件の間には二年の時間差がある。
柯氏が「利益供与」の一線を越えたかどうかは、法律上の議論として成立する。しかし、それが直ちに「犯罪」となるかは見解が大きく分かれる。明確な金流が立証されないまま十一か月もの長期勾留を続け、逃亡しないと明言して保釈や電子足輪の装着を申し出ても、なお延々と勾留を延長するのは、比例原則を著しく逸脱している。柯氏は決して忘れないだろうし、賴清徳総統もこの検察官たちを記憶に刻むべきである。民進党と賴総統の支持率が急落する中、その責任の一端が検察官にあることは疑いない。