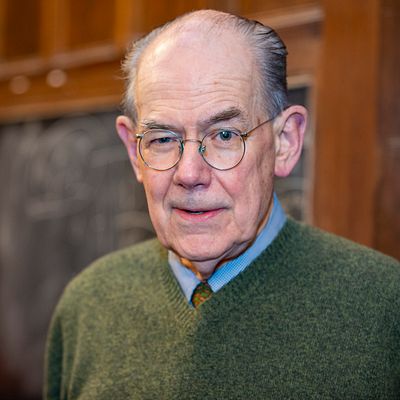賴清德520就任後の対中国戦略
総統賴清德は520(5月20日)の就任後、520就任演説、愛琿条約、国連総会2758決議が台湾に関与しないこと、平和協定を絶対に締結しないことなど、北京に対して綿密な組み合わせ攻撃を繰り出している。双十節(10月10日)の国慶節式典で、賴清德は国民に対岸を「祖国」と呼ばないよう注意を促した。賴清德は、「中華人民共和国は絶対に中華民国国民の祖国にはなり得ない」と指摘し、むしろ「中華民国が中華人民共和国の75歳以上の国民の祖国かもしれない」と述べた。しかし、中華民国は台湾、澎湖、金門、馬祖で75年間根を下ろしており、「もはやこの関係について議論する必要はない」と付け加えた。
賴清德の「祖国論」が再び波紋を呼ぶ
賴清德のこの「祖国論」が再び波紋を呼んでいる。両岸の関係者が『風傳媒』に明かしたところによると、国慶節の長期休暇中にもかかわらず、北京の台湾関連部門はこの件で残業し、あちこちで情報収集に奔走したという。賴清德の動機は何か、なぜあの場面であのような発言をしたのか?なぜなら、賴清德の「祖国論」は習近平の母親斉心を暗に示唆しているようで、その世代の人々はかつて中華民国に憧れ、認識していたからだ。
賴清德、強硬な姿勢を示し「民国派」を統治
北京の台湾問題専門家が『風傳媒』に分析を語ったところによると、3つのポイントがあるという。
まず、賴清德は北京に対して前総統の蔡英文よりもさらに強硬な姿勢を示そうとしている。賴清德は蔡英文路線を踏襲すると強調していたが、実質的には「蔡規賴随」(蔡英文の規則に賴清德が従う)ではなく、蔡英文の「中華民国台湾」や「4つの堅持」の論述よりもさらに一歩踏み込んでいる。賴清德が突然「祖国論」を持ち出したのは、実質的に「二国論」のアップグレード版であり、賴清德が中華人民共和国に言及する際に「隣国」という言葉を使用したことは、過去の「対岸」という表現とは異なり、両岸関係を説明するものだ。賴清德の「隣国論」は、本質的にはやはり「二国論」である。

次に、賴清德は北京に対して積極的に攻勢をかけており、蔡英文の「挑発しない、冒険しない」という立場とは異なる。今や賴清德は受動的に対応するのではなく、積極的に「二国論」を持ち出し、しかも止まることなく連続して発言している。これは、国際社会の支持と同情、特にアメリカの支持に後押しされているからだ。バイデン政府が9月に台湾に史上最大の武器売却を承認したことで、賴清德は北京と対決する自信を得て、名実ともに「実務的な台湾独立活動家」となっている。
(関連記事: 習近平の側近が分析、米中関係の行方 トランプ復活で主導権構図に変化も | 関連記事をもっと読む )第三に、賴清德が「中華民国は祖国である」という表現を使用したのは、蔡英文の過去の演説には現れなかった表現であり、賴清德が「中華民国」というカードを手に持っているからだ。中華人民共和国と中華民国を並列し、後者を「祖国」と呼ぶのは、「中華民国派」を統治するためである。賴清德の「祖国論」の言い方は、一般の中国大陸の人々にとっては少し新鮮味がある。なぜなら、大陸には一部の高齢者や自由主義者が「民国派」であり、民国時代にまだ期待と憧れを持っているからで、これには統治の意味合いがある。