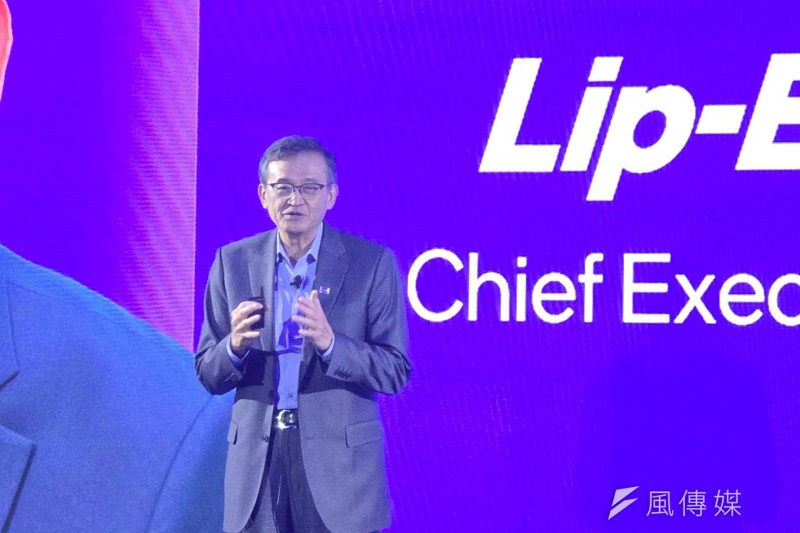トップ ニュース 政府が大株主に!インテル出資の衝撃 TSMCにも迫る「技術主権リスク」
政府が大株主に!インテル出資の衝撃 TSMCにも迫る「技術主権リスク」 TSMCの魏哲家董事長(左)と米国のドナルド・トランプ大統領(右)は、2025年3月3日にホワイトハウスのルーズベルトルームで記者会見を行った。(AP通信)
アメリカ政府は《CHIPS・科学法》の未執行補助金や国家安全保障プロジェクト資金を株式に振り替え、インテルの大株主となった。取引はすでに8月26日に完了し、総額89億ドル(約1兆3000億円)、持ち株比率は約10%、取得価格は1株20.47ドル。ホワイトハウスは「一銭も使っていない。元々は補助金を形を変えて提供しただけ」と説明する。しかしインテル自身は、この取引が両刃の剣であることを認めている。公開資料には「政府が株主になることで国際市場の信頼低下、補助政策の不透明化、意思決定の政治化、さらには株式希薄化のリスクがある」と明記されている。
では、この動きがTSMC(台湾積体電路製造)にどう関係するのか。影響は小さくない。大きく分けると3つの論点がある。
一、 米国生産拠点──政策支援を得た者が市場を先取り 短期的に見れば、インテルへの資本投入は資金繰りを支える即効性のある「強心剤」だ。永豐投顧は「米政府の出資は資金圧力を緩和し、先端プロセスや増産を後押しする」と評価する一方で、「経営への介入や政治リスクを伴う」と指摘する。
一方、TSMCにとって重要なのは投資ペースと政策の中立性だ。市場では一時「米政府がTSMCに出資するのでは」との懸念が流れたが、現政権が「TSMCに出資する意向はない」と発信したことで、短期的には安心材料となった。政治色が強まるリスクをひとまず避けられた格好だ。
インテルCEOの陳立武氏は「われわれは政府の補助を必要としないが、米国政府が株主パートナーとなることを大いに歓迎する」と述べた。(写真/魏鑫陽撮影)
さらにTSMCは市場を意識し、「米国での投資計画はすでに発表済みの1650億ドル(約24兆2500億円)であり、それ以上でも以下でもない」と明言。空虚な数字ではなく、人材・材料・パッケージ・装置・研究開発まで連動する段階的なロードマップであることを強調した。
投資機関の見通しでも、今後10年間で米国は半導体生産の「中核拠点」となり、TSMCは米国における先端プロセスで独占的地位を確立するとの観測がある。実際には「2ナノを含む先端プロセスの3割を米国で生産する」というシナリオも描かれている。これは単なるスローガンではなく、供給網と地政学の緩衝材として現実的に検討されているものだ。
二、輸出規制──価格と需要の再配分が「現地生産」の必要性を押し上げる 次の焦点は輸出規制による新たな枠組みだ。華南投顧は、一、H20やMI308の販売制限、二、収益の15%分担、三、H20価格の18%上昇リスク、四、IDC用半導体の50%国産化──この4点を挙げ、いずれもAIサプライチェーンにおける資金繰りや納品ペースを左右する「変数」と分析する。
この4点を組み合わせると、現象はさらに鮮明になる。第一に、中国向け販売には「許可と分担」が事実上の追加税として課される。第二に、価格上昇は中国以外の市場案件を優先させる圧力になる。第三に、承認プロセスやコンプライアンスコストの増大によって、急ぎの注文はより近い生産拠点へ振り分けられる傾向が強まる。結果として、米国内の先端生産能力は政策によって稼働率が押し上げられることになる。TSMCがアリゾナ州で進める2段階・3工場の先端ファブと先進パッケージ拠点にとっては、確かな需要の裏付けとなる。
NVIDIA創業者兼CEOの黄仁勳氏は、ホワイトハウスに働きかけた末にH20の対中販売を認めさせるまでに至った。(写真/劉偉宏撮影)
数字でもすでに兆候は表れている。華南投顧によれば、H20の販売禁止はNVIDIAに150億ドル(約2兆2000億円)規模の売上損失をもたらす可能性がある。一方でNVIDIAはTSMCに対しH20生産を30万枚追加発注し、中国向け年間出荷は150万個、売上は230億ドル(約3兆4000億円)規模に達すると見込まれている。中国政府がH20をどう扱うかは依然不透明だが、AI半導体の需給バランスの変化は数字に如実に現れ始めている。
三、技術主権──拡張と機密保護の間でどう線を引くか 最後の論点は「技術主権」と情報保護だ。表面的には地味だが、最も致命的になり得るリスクである。ここ数週間、台湾でも「技術流出」をめぐる議論が盛んになっている。永豐投顧は、「TSMCの対米投資規模は1650億ドルで固定されており、政治的な数字遊びではない」と強調。そのうえで、米国展開の一歩ごとに分権的な権限管理、データの非機微化、サプライチェーンのセキュリティ対策を組み合わせなければ、生産能力が倍増する一方でリスクも倍増しかねないと警鐘を鳴らす。
TSMCはなぜ米国政府からの出資を拒んだのか──その背景が問われている。(資料写真)
インテルの出資事例はその教訓を示す。政府が「投資家」の立場を取ると、技術と経営の境界は曖昧になる。インテルのリスク開示文書にも「意思決定が政治化し、国際的な調達が縮小する可能性がある」と明記されていた。同じ仕組みは、調達方針やローカル生産比率、輸出許可制度を通じて外国企業に作用することもあり得る。TSMCは単に投資収益を計算するのではなく、「情報開示とコンプライアンス」という長期コストまで見据える必要がある。
TSMCに必要なのは「中立性」を資産化すること 総じてみれば、3つの論点はいずれも同じ方向を指している。すなわち、米国での生産拡大は避けられないが、「ガバナンスの中立性」を制度として構築し、顧客にも政策当局にも理解される形で資産化することが鍵となる。ホワイトハウスが「TSMCに出資する意思はない」と明確に示したのは重要な一歩だ。しかし輸出規制の新たな枠組みは、非中国市場での単価上昇や審査の長期化を伴い、米国拠点の柔軟性を一層重視させる。
永豐投顧は「米政府は実際には89億ドルを投じており、補助金を株式に変えただけだ」とも指摘する。つまり政治経済のロジック自体は変わっておらず、手法が変化したにすぎない。TSMCにとって真の防衛線は、先端ノードと先進パッケージ技術の優位性、安定したサプライチェーン、そして「特定の主権に従属していない」という中立性そのものなのである。
更多新聞請搜尋🔍風傳媒日文版
最新ニュース
台湾の声を世界へ 《島の聲》が大阪万博で初演 杜思慧監督「台湾の信仰と多様性を届けたい」 台湾文化部が主導する《We TAIWAN》文化プロジェクトの中核を担う舞台《島の聲:廟前の感謝の舞台》が、2025年8月26日、大阪・関西万博の夢洲会場で初演を迎えた。台湾各地の伝統芸能、宗教儀式、音楽、舞踊、さらに現代表現を融合させた70分のステージは、台湾文化の「聲(声)」を世界に届ける挑戦的な試みとして注目を集めた。文化部のプロデュースによる《We T......
大阪・関西万博で《We TAIWAN》初公演 台湾国旗を背景に堂々の舞台演出、観客から大反響 文化部主導の文化プロジェクト《We TAIWAN》の一環として、《島の聲:廟前の感謝の舞台》が2025年8月26日、大阪・関西万博夢洲会場の公式屋外ステージ「Pop-Up Stage North」で初公演を迎えた。台湾の文化団体が、国旗を背景に正式なステージで堂々と演出を行うのは初めてであり、現地の台湾人観客のみならず、日本人来場者からも大きな反響を呼んだ。......
陸文浩氏の視点:中国軍機、台海で昼夜を問わぬ異常活動 Ro-Ro船団を護衛し南下集結か 最近、中国軍機が台湾海峡で昼夜を問わず異常な活動を見せている。その背景には、中国民間のロールオン・ロールオフ(Ro-Ro)貨物船団が南下する動きがあり、軍機が護衛する形で集結している可能性が指摘されている。中露の公式報道によれば、第6回中露合同巡航は8月20日に終了し、西太平洋の海域で分離行動に移った。筆者の推測では、中国東部戦区海軍の052D型駆逐艦「紹興......
論評:台中市長・盧秀燕がカギを握る 国民党リーダー争いの行方 台湾で行われた大規模リコール運動が連敗に終わり、民進党内部では「敗因探し」と「責任の押し付け合い」が続いている。まるで敗北は自分たちのせいではないと言わんばかりで、リコール主導派が使っていた自虐的な言葉「我々は負けたのではない、まだ勝っていないだけ」を体現するかのような状況だ。しかし、与党・民進党の総統である頼清徳氏は本当に安泰なのだろうか。8月23日の記者......
台湾民進党で内紛拡大 柯建銘氏に退陣圧力 頼清徳政権の側近らが「党団幹部改選署名書」を推進 台湾では大規模リコールでの連敗を受け、民進党内部での動きが加速している。新任の民進党秘書長・徐国勇氏は26日午後、党本部で各派閥の会議を招集し、大統領府秘書長の潘孟安氏に対し、民進党団総召集人の柯建銘氏の処遇について協議するよう要請した。協議が不調に終わった場合、派閥横断の立法委員が連署を行い、党団幹部の改選を迫る可能性がある。この「署名書」の存在が明らかに......
トランプ氏がプーチン氏に「最後通告」 停戦拒否ならロシア経済に前例なき制裁圧力 米国のトランプ大統領は8月26日、ホワイトハウスで開かれた閣議において明確な姿勢を示し、ロシアのプーチン大統領がウクライナ問題で停戦合意を拒み続けるなら、米国は大規模な経済制裁を発動すると表明した。これは1月20日の大統領就任以来、トランプ氏がウクライナ戦争に関して示した最も強硬な公開発言である。メディアからプーチン氏が具体的な結果に直面するかどうかを問われ......
沈旭暉コラム:ロシア・ウクライナ和平会議の三つの構造的難題 プーチン氏とゼレンスキー氏が直接会談に臨む可能性が高まるなか、各方面がこれまで避けてきた最も厄介な問題に向き合わざるを得なくなっている。戦争は最終的に交渉によって終結するものであり、概念的にはこれは否定できない。たとえ「城下の盟」であっても、交渉という形式を取らざるを得ないのである。問題は、どのように交渉するかに加え、どれほどの時間を費やすかという点である。......
WBC2026、日本でNetflix独占配信決定 地上波中継消滅の可能性に読売新聞社が声明 読売新聞社は8月26日、米動画配信大手Netflixが2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)を日本国内で独占生配信することについて声明を発表した。今回の決定により、WBC全47試合がNetflixでのみ視聴可能となり、過去5大会で行われてきた地上波での生中継が消える可能性が高まった。読売新聞社は声明の中で「今後も東京プー......
吳典蓉コラム:頼清德総統は台湾人に謝罪が必要 台湾総統という職に対する敬意から、たとえ少数派の総統であっても一定の光環は伴うものだ。しかし、大規模リコールの惨敗を経た頼清徳氏にはもはやその光環は残っていない。野党からは嘲笑され、与党内からも「事を成せない」と罵声を浴び、頼氏の一挙手一投足はネット上で二次創作のネタにされる始末である。要するに、いまの頼氏は発言力をほとんど失っているのである。それにもかかわ......
地球温暖化が新段階へ 東京大学・今田由紀子准教授「異常気象は温暖化なしでは起き得なかった」 公益財団法人フォーリン・プレスセンター(FPCJ)は8月26日、「この異常気象は気候変動のせい?」をテーマにオンラインプレスブリーフィングを開催し、東京大学大気海洋研究所の今田由紀子准教授が登壇した。会見は日本語で行われ、英語の逐次通訳も提供された。地球温暖化は新たな段階に今田氏は冒頭、近年の極端気象と地球温暖化の関連を明らかにする「イベント・アトリビューシ......
米メディアが「世界5大火薬庫」を警告 最大リスクは台湾海峡危機、誤判断で全面戦争の恐れ 第二次世界大戦の終結から80年が経過したが、戦火の影は今も消えていない。米国の政治専門誌『ポリティコ』(Politico)は25日、今後5年間で世界規模の戦争が勃発するリスクは想像以上に近いと警告した。わずかな誤判断や軍事的偶発事態、さらにはハッカー攻撃さえも、24時間以内に地域的な摩擦を全面戦争へと押し上げる可能性があるという。今年5月の印パ間のミサイル相......
天気予報》台風発生の恐れ 台湾で猛暑続く、新北・桃園で38度超 午後は雷雨に警戒 台湾の中央気象署によると、本日(28日)も蒸し暑い天気が続き、新北市や桃園市では摂氏38度を超える高温に警戒が必要である。午後には中南部や北部山間部で強い雨が降るおそれがあるという。現在、フィリピン東方の海上では熱帯性の雲の塊が発達と消散を繰り返しており、新たな熱帯系統が形成されるかどうかが来週の観測の焦点になるとしている。好天は長く続かず!この日から湿......
柯建銘は民進党の孫文か 林濁水「党内に異論なし 愚昧では敗北必至」 726、823の二度にわたる大規模なリコール失敗を受け、民進党の立法院団幹事長である吳思瑤、書記長の陳培瑜などが先日、団職を辞任すると表明した。しかし、大リコールのリーダーと見なされている総召集人の柯建銘は動じることなく、「あと1週間しかないのに辞めてどうする?朝小勢は戦い続けるしかない」と述べた。この点について、前立法委員の林濁水はフェイスブックに投稿し、......
台湾北部でM6.0地震 台北・宜蘭で震度4 防災警報システム作動 台湾・中央気象署は8月27日21時11分、宜蘭県近海を震源とするマグニチュード6.0の地震が発生したと発表した。震央は宜蘭県政府の北東22.1キロ(北緯24.88度、東経121.91度)、震源の深さは112キロだった。今回の揺れにより、台北市や宜蘭県では震度4を観測した。地震規模は「原子爆弾の半分」に相当中央気象署の顕著有感地震報告(第119号)によると、今......
九三軍事パレードを前に 中国無人機群が台湾に照準 米国を上回る強みも「侮れない」 中国で開催される「九三軍事パレード」では、これまで秘密裏に開発されてきた無人機群が公開展示される見通しだ。これらは「協同作戦航空機」(CCA)とも呼ばれ、有人機と連携して戦闘に参加する「忠実な僚機」として注目されている。国防安全研究院の舒孝煌副研究員は『風傳媒』の取材に対し、現在確認されている中国無人機の多くはステルス性能を備え、戦闘機への奇襲や防空網突破、......
独自》台湾、米国に市場全面開放を約束 企業投資は4年で2,500億ドル規模へ 米国のドナルド・トランプ大統領が各国に「相互関税」を課すと打ち出して以来、台湾もその波に飲み込まれている。政府は当初「夜は安心して眠ってほしい」と国民に呼びかけたが、最初に示された税率は32%に達し、現在も20%という高水準のままだ。台湾メディアは一時、政府が最大4000億ドル規模の対米投資計画を準備し、日本と同水準の15%関税を目指していると報じた。《風傳......
論評:「どの産業も犠牲にしない」は幻想か 台湾・頼総統の対米関税交渉に冷ややかな視線 国際情勢が不安定さを増すなか、台湾の頼清徳総統はなお自己満足的に「ユートピア」に生きているかのように見える。米大統領ドナルド・トランプ氏と「双方が得をするゲーム」が可能だと幻想を抱き、さらに「どの産業も犠牲にしない」と言い切ったのだ。その路線をなぞるように、対米交渉の責任者である鄭麗君副行政院長も国会で同じ言葉を繰り返した。しかし与党内からも冷ややかな反応が......
調査:台湾海軍の「言えない弱点」 中国最新艦隊に直面、今も百年前の水雷を運用 四方を海に囲まれた台湾にとって、海軍は安全保障の要だ。しかし近年、中国人民解放軍の海軍力は急速に拡大し、艦艇数ではすでに世界一に。最新鋭艦の配備も進む中、防衛に立つ台湾海軍の艦艇は明らかに劣勢を強いられている。2025年の漢光演習で頼清徳総統が視察した布雷訓練は、海軍が真剣に演じる一方で、水面下の大きな弱点を浮き彫りにした。台湾は今も「百年前の兵器」に依存せ......
TSMC米国投資の内幕 ルートニック長官「魏CEOに直接圧力」暴露 米トランプ大統領の象徴である「アメリカ・ファースト」経済政策が、より強硬で取引色の濃い形でワシントンに戻ってきた。26日、米商務長官ハワード・ルートニック氏がCNBCの経済番組《スクウォーク・ボックス》に出演し、衝撃的な証言を次々と明かした。彼はインテルから110億ドル(約1兆6,000億円)の補助金を出す代わりに株式10%を政府が取得した交渉の内幕を語った......
李在明大統領、トランプ氏と会談後にCSISで演説 「国益中心外交」と韓米同盟強化を強調 米国大統領トランプ氏との会談を終えた直後、韓国大統領李在明(イ・ジェミョン)氏は25日、ワシントンのシンクタンク「戦略国際問題研究所(CSIS)」で外交政策演説を行った。満席となった米国の政界関係者や学者を前に、李在明氏は「国益中心の実務外交」を核心路線として掲げ、政変後の時代において韓国をいかに導き、米中対立、北朝鮮の核脅威、国内の分裂といった複雑な課題の......
中国「九三軍事パレード」参加めぐり日中対立激化 日本は各国に慎重対応を要請 日本政府は最近、外交ルートを通じて各国に対し、中国が抗日戦争勝利80周年を記念して実施する「九三軍事パレード」に参加しないよう呼びかけた。この動きに中国外交部が注目し、26日には「日本側に対し厳正な申し入れを行い、説明を求めた」との声明を発表し、大きな議論を呼んでいる。中国、日本に情報の明確化を要求報道によれば、日本政府は在外公館を通じて各国に対し、今回の中......
天気予報》台風14号(ノンファ)1日発生へ 全台湾3日連続雷雨 中央気象署は本日(27日)、台北市、新北市、桃園市など6県市に高温情報を発表した。新北市と桃園市では38度に達する見込みである。気象専門家の呉徳栄氏によれば、30日までは各地で暑さが続き、午後には激しい雷雨に注意が必要だという。来週は南方の水蒸気が北上し気温はやや下がるが、引き続き午後の雷雨に警戒すべきである。台風14号ノンファ発生の可能性中央大学大気科学系......
トランプ氏は台湾を取引材料に? 豪専門家が「中国譲歩」の危険性を警告 米国大統領トランプ氏が就任して以降、従来の外交政策や経済措置を大きく転換したことで、オーストラリアや欧州連合(EU)といった「中間的立場の国々」は難しい立場に置かれたが、こうした状況への備えは十分でなかった。最近、オーストラリアの専門家は、台湾をめぐる問題において、トランプ氏がロシアのプーチン大統領に対するのと同様の姿勢を見せ、中国に譲歩する可能性があると指......
舞台裏》台湾・国民党リコール全勝も党内混乱 朱立倫氏退任宣言と盧秀燕氏辞退で次期主席不透明に 台湾で823リコール戦が幕を閉じ、国民党はリコール推進団体と民進党に対し圧倒的勝利を収めたものの、党内の歓喜は長く続かなかった。次期党主席が不透明なままという不安が、すぐに喜びをかき消したのである。国民党主席の朱立倫氏は、823当日の夜に「安心してバトンを渡し、自らは再任を目指さない」と明言。翌24日には、次期党首として党内から最も期待されていた台中市長の盧......
TSMC投資の次は全面関税撤廃要求 頼清徳政権に「屈従批判」拡大 台湾で8月23日に行われた「823第2波リコール案」の開票結果が明らかとなり、民進党が推進した大規模リコールは32対0で全敗に終わった。新竹市長・高虹安氏に対するリコール案も不成立となった。フェイスブック上で時事批判を展開する人気ページ「エンジニアが見る政治」は、総統・頼清徳氏と民進党団総召・柯建銘氏が主導した「史上最大のリコール劇」が終結したと指摘。一年間......
東京都心、猛暑日が10日連続で過去最長記録更新 累計23日で年間最多に 日本列島は高気圧に覆われ、各地で危険な暑さが続いている。東京都心では27日午前10時42分に35.3度を観測し、10日連続で最高気温が35度以上の「猛暑日」となった。これは2022年に並んでいた最長記録を更新したものである。また、今年の「猛暑日」の日数も累計23日に達し、過去最多を記録した。東京の街並みを猛暑が覆い、強烈な日差しが照りつけている。(AP通信)......
日本政党支持率最新調査 参政党が支持率9.9%で野党第1位に浮上 日本の最新世論調査によれば、結成からわずか5年の参政党の支持率が9.9%に達し、与党・自民党に次ぐ位置につけたことが分かった。7月の参院選で「日本人ファースト」を掲げた参政党は、30代と40代の支持を最も多く集めている。産経新聞とフジニュースネットワーク(FNN)が8月23日と24日に共同で実施した政党支持率調査では、自民党が22.2%で首位となった。続いて......
評論:台湾の頼清徳総統、リーダーシップ欠如の声広がる リコール大敗の余波 台湾で行われた7月26日の大規模リコールに続き、8月23日の第2波リコールも全て否決され、国民党の立法委員は一人も失職しなかった。逆に「反対票」が大きく上回り、結果は「31対0」の全敗。予想通り、頼清徳総統の「敗戦後の談話」もまた、期待を裏切る内容だった。
旧原発再稼働の検討──経営者・童子賢氏への慰めか?そもそも総統がリコール選挙に深く関与する必要はなかっ......
台湾・賴清徳総統に「決まり文句ばかりで心に響かない」 民進党寄りの学者が苦言 台湾では大規模リコールが正式に幕を閉じ、最終的に31件すべてが成立せず不発に終わった。だが民進党内部からは早くも反省と批判の声が上がっている。米国在住の教授で評論家としても知られる陳時奮氏(筆名・翁達瑞)は25日、フェイスブックに投稿し、賴清徳総統の発信には「決まり文句ばかりで心に響かない」と苦言を呈した。「演説や投稿を支える文字幕僚の責任もあるが、賴総統自......
インド人はなぜ台湾を嫌うのか?世論調査に見る背景 ――中国の影と共同利益、若い世代のまなざし 2023年の国際世論調査で、インドは少数派ながら「台湾に否定的な印象」を持つ国として浮かび上がった。43%もの回答者が台湾に「ネガティブな見方」を示し、この数字は各国と比べても異例だ。「インド人はなぜ台湾を嫌うのか?」という疑問が改めて突きつけられている。インドのジャワハルラール・ネルー大学(JNU)国際研究学院の研究員であり、『太平洋の危機:軍事バランスと......
顏厥安氏の視点:台湾「ブルーシート政権」化 リコール大敗で卓内閣に総辞職要求の声広がる 災害に見舞われた人々の姿を政治にたとえるのは適切ではないかもしれない。だが、台湾の賴清徳総統が被災地で脚立を使って「視察ポーズ」を演出した場面を思えば、災後の風景と台湾政治の現実を重ねるのもあながち的外れではない。大規模リコールで大敗を喫した賴政権・卓内閣は、すでに「ブルーシート政権」(台湾では「帆布政権」)と化している。崩れた家屋をブルーシートで覆い、見か......
台湾・民進党若手党員が見る賴清徳総統 「退屈で自己愛的」「情緒的価値を与えられない」 2024年に再び政権を握った台湾民進党だが、2025年の「726」「823」のリコールや国民投票では惨敗を喫した。その一方で、国民党は「南方公園」風の動画に「ライアー(嘘つき)校長」と揶揄したキャラクターを登場させ、賴清徳総統を批判。これが若者層で拡散され、ネット上で広がりを見せている。
台湾のオンラインメディア《美麗島電子報》が2025年7月に行った世論調......
TSMC「米国は出資せず」明言 トランプ氏がインテルを選んだ背景と郭明錤氏の分析 米国のトランプ大統領は、米政府がIntelの10%の株式を取得したと発表し、市場の注目を集めた。また、TSMCへの出資の噂も伝えられたが、TSMCの魏哲家董事長は22日夜に取材を受け、「米国は出資しないと発表した」と明らかにし、外部の疑念を払拭した。天風国際証券のアナリスト郭明錤氏はこれについて重点分析を行い、なぜこの出資モデルが「TSMCとサムスンには適用......
李在明氏、台海リスクを前に訪米決断 トランプの対中要求に揺れる韓国外交 韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領は米東部時間8月25日、ワシントンに到着し、ドナルド・トランプ米大統領との初の首脳会談に臨む。今回の会談は、米韓同盟の新たな段階の始まりを象徴すると同時に、防衛負担、中国戦略、朝鮮半島の安全保障バランスをめぐる双方の重大な試練ともみられている。
李在明氏は選挙戦の過程で、国家利益のためには極端な姿勢も辞さず米国との関係を守......
台日作家交流座談会東京で盛況 楊双子と角田光代が文学対話 台湾文学を代表する作家・楊双子氏と、日本を代表する直木賞作家・角田光代氏の対談イベント「在台湾、在日本、持続して物語を書き続ける」が23日、東京都内の台湾文化センターで開催された。会場は満席となり、出版界や学術関係者を含む多くの来場者が詰めかけ、熱気に包まれた。文化部駐日台湾文化センターは毎年、日本で台湾文学の翻訳書を刊行した作家を招き、日本の作家や翻訳者、......